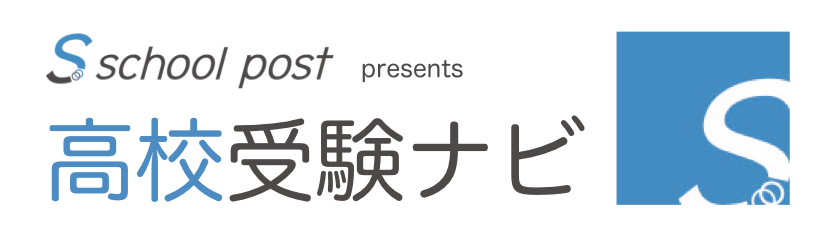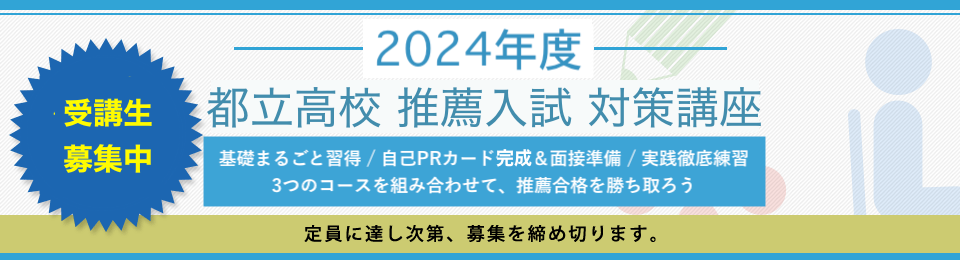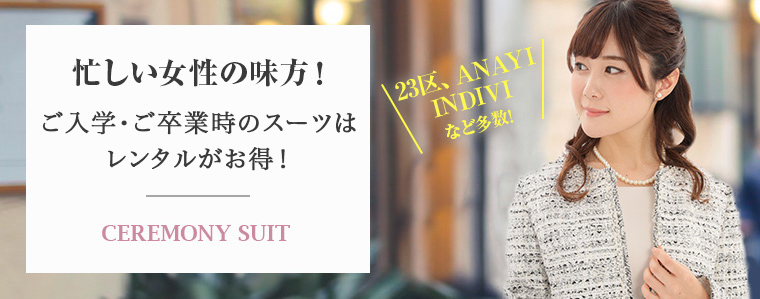中学技能教科「技術・家庭科」攻略、乳幼児分野の学習のポイント

執筆
中里 太一(なかざと たいち)
成長過程と時期・期間
| 時期の名称 | 期間 |
|---|---|
| 乳児期 | 生まれてから1歳になるまで |
| 幼児期 | 1歳から小学校入学まで |
| 児童期 | 小学校入学から卒業まで |
期間と名称をセットで覚えましょう。
乳幼児の体の発達
(1)体の発達
| 生まれた時 | 1歳 | 4歳 | |
|---|---|---|---|
| 身長 | 50cm | 75cm | 100cm |
| 体重 | 3,000g | 9,000g | 15,000g |
身長は、1歳で生まれた時の1.5倍。4歳では2倍になります。体重は、1歳で、生まれた時の3倍。4歳では5倍になります。
テストでは何倍になるかを答えさせる問題が多いです。数字のイメージを持ってもらおうと思い、生まれた時、1歳、4歳の表を作りました。たった4年でとても大きくなるイメージが持てるかと思います。
(2)運動機能の発達は2パターンを覚えよう
① 上から下に向けた発達
生まれた直後は、首が据わっていないため、頭がグラグラした状態にあります。それが時間の経過と共に、首がしっかりしてきます。そして、背骨、腰の順番にしっかりしてきて、おすわり→ハイハイ→伝い歩き→ひとり歩きと、段階的に下方向に発達していきます。
② 中心から末端に向けた発達
赤ちゃんは最初、腕も満足に動かせません。それが腕全体からしだいに手先に向かって発達し、時間の経過と共に指先まで発達していきます。このように腕、手先、指先と徐々に先端に向かっても運動機能が発達していきます。
生理的機能は大人との比較で理解する
- 幼児は成人と比べて体温が高い
→汗をかきやすい
→十分な水分補給が必要 - 幼児は成人に比べて疲れやすい
→活動のためのエネルギーを蓄えなければいけない
→多くの睡眠時間が必要
乳幼児の心の発達
幼児期には、体の成長にあわせて、心も発達していきます。ここでは用語とその意味をしっかりと
覚えましょう。
(1)覚えたい用語と意味
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 自立 | 自分の力で生活できること |
| 自律 | 場面に応じて自分の感情や行動をコントロールできること |
| 情緒 | 愛情・喜び・悲しみ・心配など |
| 社会性 | 人に対して示す、反応や働きかけのこと |
- 自立の例としては、ひとりでトイレに行ける、洋服を一人で脱いだり着たりできることをいいます。
- 自律はたとえば、友達が3人いておもちゃがひとつしかない場合に、おもちゃで遊びたいけれど、他に友達がいるから独り占めしないで、順番で交代することができるようなものを指します。
- 情緒は、「感情」という言葉にとても近いです。ただし、この分野では「感情」とは言わず「情緒」と表現します。
(2)基本的生活習慣
- 意味:生きていくために毎日繰り返されることを自分でする習慣のこと
- 例:食べる、寝る、トイレに行く
(3)社会的生活習慣
- 意味:他人と気持ちよく生活するために必要な習慣のこと
- 例:約束を破らない、マナーを守る
乳幼児の遊び
(1)乳幼児の一日
- 睡眠時間が多い
- 遊びが中心
- 胃が小さいため3回の食事以外におやつを食べる
(2)遊びで得られるもの
- 運動機能発達
- 豊かな感性
- 他人とのかかわり方
(3)おもちゃ
おもちゃは、遊びのきっかけになり、想像力を広げ、遊びを豊かにしてくれる役割を持ちます。おもちゃを選ぶときのポイントと、おもちゃの安全マークについて紹介します。
① おもちゃを選ぶポイント
- 幼児の発達段階にふさわしい物
- 扱いやすい大きさで、十分に使いこなせる種類や数であること
- いろいろな使い方ができるもの
- 色彩や形が美しく、安全で丈夫なもの
1歳児に500ピースのパズルをやらせてもできませんよね。ですから、500ピースのパズルは「幼児の発達段階にふさわしい物」と「扱いやすい大きさで、十分に使いこなせる種類や数である」という条件を満たしていません。また、「いろいろな使い方ができるもの」というのは、おもちゃの役割は、幼児の想像力を養うこともあります。ですから、さまざまな使い方ができる方が望ましいですよね。
乳幼児は、まだ判断能力に乏しく、力の加減も分かりません。ですから、安全であるということは最も重要です。
① おもちゃを選ぶポイント
最後におもちゃについているマークと意味をあわせて覚えましょう。

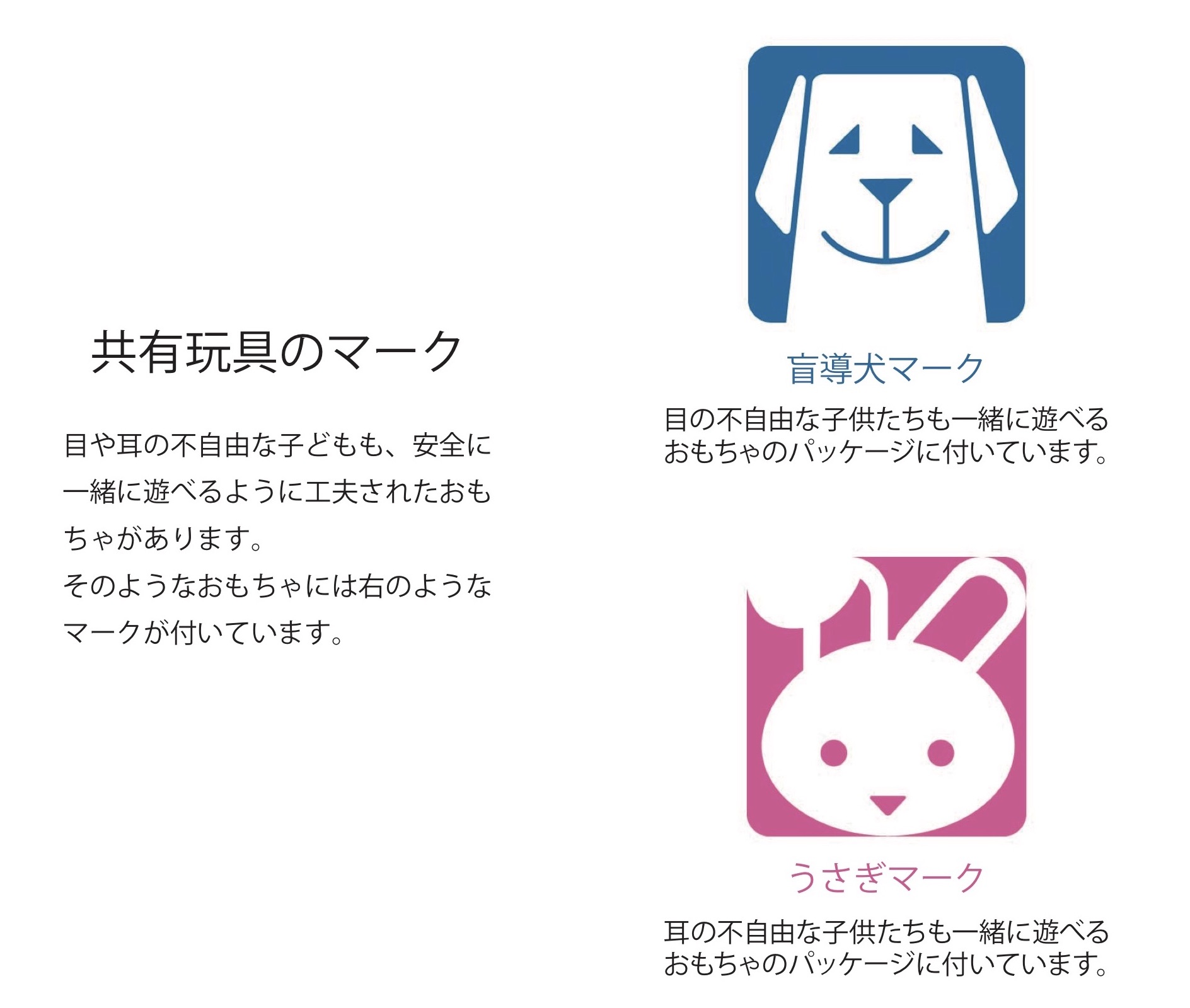
| 名称 | 意味 |
|---|---|
| STマーク | おもちゃの安全基準に合格しているもの |
| 盲導犬マーク | 目の不自由な子供たちも一緒に遊べるおもちゃ |
| うさぎマーク | 耳の不自由な子供たちも一緒に遊べるおもちゃ |
以上が、乳幼児の単元についての基本知識です。これを基本に、「基本的生活習慣の例を答えなさい」や「幼児は汗をかきやすいから、どのような対応が必要か?」というような具体例を問題で聞かれるケースもあります。後は、教科書や授業内でのプリント・ノートを使用して細かい部分も覚えていきましょう。
執筆
中里 太一(なかざと たいち)