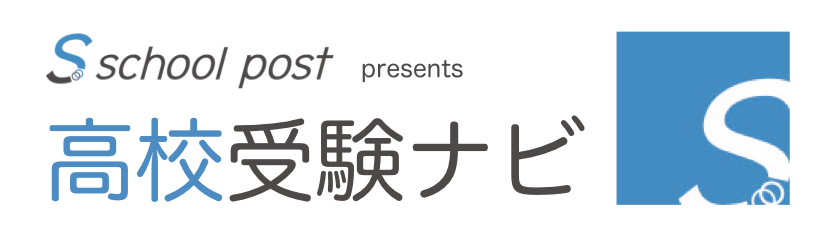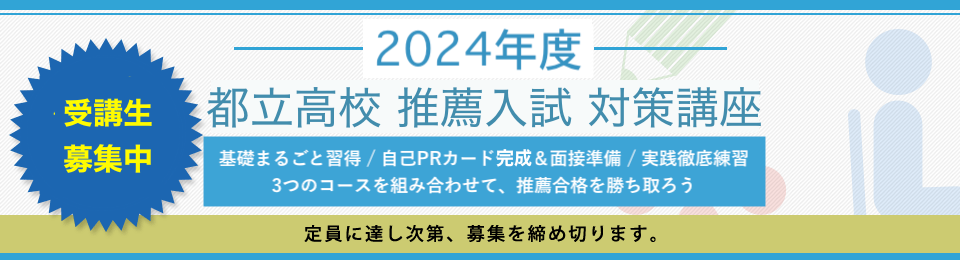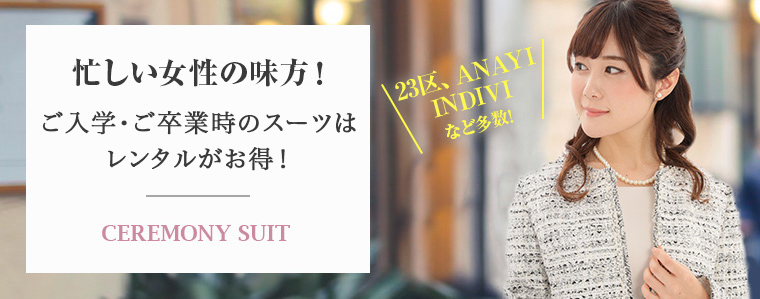【社会】の大問[2]の解説:都立一般入試の攻略法
![【社会】の大問[2]の解説:都立一般入試の攻略法](https://school-post.com/new/wp-content/uploads/2017/12/syakai_test.jpg)
執筆
石井 知哉(いしい ともや)
都立一般入試の社会、大問2の配点と構成
都立高校一般入試の社会の大問2は世界地理についての出題です。大問の冒頭で世界全体あるいはある地域の略地図を取り上げて、そこに示された国についての小問が3つ出題されています。
1問5点で合計15点の配点となります。いずれも記号で解答する問題です。
問題と配点の構成は過去15年以上変わっていません。今後も大きく変わらないと予想されます。
出題のねらいは「世界の諸地域の特色や我が国と世界の結びつきについて、地図や統計等の資料を活用して、地域的特色を考察する能力をみる」とされています。
(東京都教育委員会「東京都立高校入学者選抜学力検査結果に関する調査」より引用)
- 気候・自然環境に関する問題
- 時差に関する問題
- 産業・貿易に関する問題
の3つが主な出題タイプです。
以下、それぞれのタイプごとの攻略方法を紹介します。実際に都立高校入試の社会の問題を見ながらご覧頂くと効果的です。
問題・正答は東京都教育委員会のホームページで公開されています。
- 【平成26年度】
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/2014/pr140224n-mondai.htm - 【平成25年度】
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/pr130223n-mondai.htm - 【平成24年度】
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/pr120223n-mondai.htm - 【平成23年度】
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/pr110223n-mondai.htm - 【平成22年度】
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/pr100223n-mondai.htm
気候・自然環境に関する問題の攻略の方法
主に問1または問2で出題される気候・自然環境に関する問題についてみていきます。
【出題の傾向】
<過去の出題内容>
- 平成11年度
問2:気候についての記述から、略地図中の国に当てはまるものを選ぶ - 平成12年度
問1:気候についての記述から、略地図中の地域に当てはまるものを選ぶ - 平成13年度
出題なし - 平成14年度
問3:気候についての記述から、略地図中の地域に当てはまるものを選ぶ - 平成15年度
問1:年平均気温、年降水量についての表から、略地図中の国に当てはまるものを選ぶ - 平成16年度
問2:気候についての記述から、略地図中の国に当てはまるものを選ぶ - 平成17年度
問2:平均気温を示した表を手がかりに、当てはまる国を選ぶ - 平成18年度
問1:気候についての記述と雨温図から、略地図中の都市に当てはまるものを選ぶ - 平成19年度
問2:気候についての記述から、略地図中の国に当てはまるものを選ぶ - 平成20年度
問2:雨温図を手がかりに、略地図中から都市を選ぶ - 平成21年度
問1:雨温図を手がかりに、略地図中から都市を選ぶ - 平成22年度
問1:2つの雨温図に対応する都市をそれぞれ略地図中から選ぶ - 平成23年度
問2:気候についての記述から、略地図中の国に当てはまるものを選ぶ - 平成24年度
問1:2つの雨温図に対応する都市を両端とする道路をそれぞれ略地図中から選ぶ - 平成25年度
問1:4つの雨温図に対応する都市をそれぞれ略地図中から選ぶ - 平成26年度
問1:4つの雨温図に対応する都市をそれぞれ略地図中から選ぶ
※気候・自然環境に関する情報だけでなく、時差や産業についての記述を合わせて手がかりとする場合もあります。
<出題パターンの分析>
毎年必出といっていいタイプです。必ず世界地図を用いた形で出題されます。
ここ数年は雨温図(ある地域の年平均気温と年降水量、各月の平均気温と降水量を示したグラフ)がかなり頻繁に出題されています。
平成16、19年度は、大問2以外の箇所で、雨温図を用いた日本地理の問題が出題されました。
平成22、24、25、26年度は、2つないし4つの雨温図に対応する記号がすべて正しくなければ、正答にならない問題でした。この形式になってから、“勘が当たる”ということはほとんどなくなり、非常に難しくなりました。
<求められている能力>
山脈や河川の名称といった、定期テストで求められる細かい知識は必要ありません。
・世界地図上の位置からその地域の気候の特色を見抜く知識
・気温や降水量の情報から気候の特色をとらえる能力
が求められています。
<今後の出題予測>
今後も引き続き、地図と図表・グラフを用いた出題が続くでしょう。
【攻略の手引き】
略地図とグラフを交互に見ながら、知識を活用する問題です。不慣れなままだと、知識があっても思うように得点できません。
それでは、具体的な攻略法をご紹介します。
-
ポイント1:雨温図や文章の記述から、気候の特色をつかむ
文章の記述からは直接的に情報が読み取れます。気候の特色を示した箇所には、アンダーラインを引いて目立たせましょう。
雨温図から読み取るべきは、次の2点です。①年平均気温
グラフの上に書いてあります。
・21℃以上➡熱帯…赤道に近い
・11〜20℃➡温帯…熱帯と冷帯の中間
・1〜10℃➡冷帯…北極・南極に近い
・0℃未満➡寒帯…北極・南極
地理学的に厳密にいえばそこまで単純ではありませんが、少なくとも都立高校の入試においては、上のような区分けで、気温から気候帯を判断して構いません。②各月の平均気温
グラフ内の折れ線グラフに着目しましょう。
・どの月も大きな変化がなく気温が高い➡熱帯気候…赤道に近い
・どの月も大きな変化がなく気温が低い➡寒帯気候…北極・南極
・6〜8月が最も高い➡北半球に位置する
・6〜8月が最も高い➡南半球に位置する
ということが判断できます。こうして判断したことを雨温図の近くに簡単にメモしておくと、ミスが減ります。
-
ポイント2:略地図上で示された地域の気候の特色をつかむ
まず、はじめに、地図中に赤道を書き込みましょう。
原則として、
赤道に近い場所➡気温が高い
北極・南極に近い場所➡気温が低い
という図式が成り立ちます。ここから、気温が大まかにつかめます。また、赤道を境に北半球と南半球とが分かれますから、赤道の位置を正しく認識できるようにしておくことは極めて重要です。
赤道の位置は、アフリカ大陸の西側の突き出た部分や、インドネシアのあたりを目印にしましょう。ただし、平成20年度に出題されたように、ふだん見慣れない正距方位図法が示される場合もあります。教科書や地図帳で確認しておく必要があります。
こうして、赤道と北極・南極からの距離関係から、地図中の地域の気候、特に気温の特徴がよくわかります。
-
ポイント3:ポイント1と2からつかんだ情報を正しく対応させる
あとは仕上げです。解答欄に記入した4つの記号がすべて合っていてはじめて正解となります。
うっかりすると、「考え方は合っていたのに、記号を書き間違えて不正解」という悲劇に見舞われることになります。特に、選択肢が「①〜④」「A〜D」「P〜S」「W〜Z」とバリエーションが豊富で、見慣れた「ア〜エ」ではないことが多いので、注意が必要です。設問分の末尾をよく読み、解答の形式は目立つようにマルで囲んでおきましょう。こういうちょっとした丁寧な作業が0点か5点を分けます。
【目安の解答時間】
1分30秒〜3分での解答を心がけましょう。
知識ですぐに解答できるものではなく、図表からの情報の読み取りという作業が必要になります。そのため、ある程度の時間は見ておくべきです。
時差に関する問題の攻略の方法
主に問1または問2で出題される時差に関する問題についてみていきます。
【出題の傾向】
<過去の出題内容>
- 平成11年度
出題なし - 平成12年度
出題なし - 平成13年度
出題なし - 平成14年度
出題なし - 平成15年度
問1:時差を手がかりに、略地図中の国を示したものを表中から選ぶ - 平成16年度
出題なし
※ただし、この年度は大問6・問1で時差がヒントとなる問題が出題されています。 - 平成17年度
出題なし - 平成18年度
出題なし
※ただし、この年度は大問1・問1で時差をテーマとする問題が出題されています。 - 平成19年度
出題なし - 平成20年度
出題なし - 平成21年度
出題なし - 平成22年度
問1:文章で述べている時差を手がかりに、略地図中から都市を選ぶ - 平成23年度
問1:文章で述べている時差を手がかりに、略地図中から都市を選ぶ - 平成24年度
出題なし - 平成25年度
出題なし - 平成26年度
出題なし
<出題パターンの分析>
出題数自体は多くはありませんが、平成16、18年度を含めれば、過去16年間で5問の出題です。いずれの場合も、単に時差を問うのではなく、時差を手がかりに日時や都市を探り出す問題です。
<求められている能力>
学校の定期テストでも扱われるので、未知の問題タイプという印象を受けることは少ないことでしょう。
・問題の文章や地図から時差に関する情報を読み取る能力
・時差の基本ルールに基づき、経度差から時差、時差から経度差を求める計算能力
が求められています。
<今後の出題予測>
3年に1回のペースで出題されています。平成24〜26年は出題がないものの、忘れた頃に出題される可能性が高く、平成27年以降も軽視できません。
【攻略の手引き】
知識だけでなく数学的な計算が必要となるため、時差を苦手とする受験生は多いようです。しかし、時差についての基本ルールはそれほど複雑ではありません。
以下の手順を踏まえれば、攻略可能です。
-
ポイント1:時差の基本事項
まずは次の3つを確実に覚えておきましょう。①経度差15度につき時差1時間
地球は1日に1回自転しています。つまり、24時間で360度移動しているわけです。したがって、360(度)÷24(時間)=15(度)となり、15度につき1時間の時差が生じることがわかります。この計算式で求めることはできますが、あらかじめ覚えておくのがベストです。②日本は東経135度
問題文で日本の日時が示され、これに基づいて他の都市の日時や経度を求めることがほとんどです。ですから、日本の経度は覚えておく必要があります。(地図や問題文からわかる場合もあります)
日本の標準時子午線は東経135度と定められており、兵庫県明石市を通っています。③東に進むと時刻を進め、西に進むと時刻を戻す
太陽が東から昇り西に沈むように、同じ日付・時刻が訪れるのは東のほうが先です。ですから、日本より15度東では1時間進め、15度西では1時間戻します。ただし、日付変更線を西から東にまたぐと1日進み、東から西にまたぐと1日戻ります。 -
ポイント2:経度から日時を求める
平成18年度はこちらのタイプでした。
次の3つのステップで求められます。①2地点の経度から経度差を計算する
経度どうしのひき算をします。
このとき、より東に位置している方(東経の大きい方)から西に位置している方(東経の小さい方)を引きます。
西経はマイナスで考えると計算しやすくなります。例1:日本(東経135度)とロンドン(0度)
➡135−0=135 Answer. 経度差135度
例2:日本(東経135度)とイスタンブール(東経30度)
➡135−30=105 Answer. 経度差105度
例3:日本(東経135度)とロサンゼルス(西経120度)
➡135−(−120)=255 Answer. 経度差255度②時差を計算する
①で求めた経度差を、15でわり算します。例1:日本とロンドン(経度差135度)
➡135÷15=9 Answer. 時差9時間
例2:日本とイスタンブール(経度差105度)
➡105÷15=7 Answer. 時差7時間
例3:日本とロサンゼルス(経度差255度)
➡255÷15=17 Answer. 時差17時間③日時を計算する
②で求めた時差を、より東に位置している方(東経の大きい方)の日時からひき算します。
このとき、午前と午後の区別がややこしくなります。
そこで、「午後1時➡13時」「午後10時➡22時」というように、24時間表記で計算すると楽です。24時間表記で計算した結果がマイナスになった場合は、日付を1日前にしてから、マイナス分を24時から引きます。例1:日本時間1/18午後3時のときのロンドン(時差9時間)
➡15時−9時間=6時 Answer. 1/18午前6時
例2:日本時間1/18午後3時のときのイスタンブール(時差7時間)
➡15時−7時間=8時 Answer. 1/18午前8時
例3:日本時間1月18日午後3時のときのロサンゼルス(時差7時間)
➡15時−17時間=マイナス2時➡1日前の24時−2時間=22時 Answer. 1/17午後10時どうしても③の計算が苦手なのであれば、東から西に進みながら、経度差15度につき1時間ずつ時刻を前に戻していくという方法もありです。
時間はかかりますが、地道な分だけ正確です。 -
ポイント3:日時から地点を求める
平成22、23年度はこちらのタイプでした。
ポイント2で示した3つのステップを逆にたどっていく形になります。①2地点の日時から時差を計算する
時刻どうしのひき算をします。
このとき、より進んでいる方から遅れている方を引きます。午前と午後の区別がややこしくなるので、24時間表記で計算しましょう。1/18の5時と1/17の22時、というように、日付が異なるような2地点について出題されることはめったにありません。
万が一出たときは、日付の進んだ方の時刻にプラス24時間して1日戻してください。
1/18の0時は1/17の24時と同じことなので、17日の24時以降と考えることもできるのです。
したがって、1/18の5時=1/17の29時なので、1/17の22時との時差は7時間となります。例1:日本(1/18午後3時)とロンドン(1/18午前6時)
➡15時−6時=9 Answer. 時差9時間
例2:日本(1/18午後3時)とイスタンブール(1/18午前8時)
➡15時−8時=7 Answer. 時差7時間
例3:日本(1/18午後3時)とロサンゼルス(1/17午後10時)
➡15時+24時間−22時=39時−22時=17 Answer. 時差17時間②時差から経度の差を計算する
①で求めた時差に15をかけ算します。例1:日本とロンドン(時差9時間)
➡9×15=135 Answer. 経度差135度
例2:日本とイスタンブール(時差7時間)
➡9×15=105 Answer. 経度差105度
例3:日本とロサンゼルス(時差17時間)
➡17×15=255 Answer. 経度差255度③経度を計算する
②で求めた経度差を、より東に位置している方(東経の大きい方)の経度からひき算します。西経はマイナスで考えると計算しやすくなります。例1:日本(東経135度)と経度差135度のロンドン
➡135−135=0 Answer. 0度
例2:日本(東経135度)と経度差105度のイスタンブール
➡135−103=30 Answer. 東経30度
例3:日本(東経135度)と経度差255度のロサンゼルス
➡135−(255)=マイナス120 Answer. 西経120度「③の計算が難しい」というのであれば、地図上で東から西になぞりながら、時差1時間につき15度ずつ経度を減らしていくという方法が使えます。
時間はかかりますが、こちらも地道な分だけ正確です。 -
ポイント4:該当する選択肢を選ぶ
以上のプロセスを経て、答えが弾き出されます。あとはこれに合致するものを4つの選択肢から選ぶだけです。上の3つのポイントで示した手順のうち、どこか一箇所でも間違いがあれば、正解は出ません。はじき出した答えが選択肢の中にないはずです。その場合は、自分の計算ミスを疑い、もう一度計算し直してみましょう。
それでも該当する選択肢がない場合は勘違いをしているおそれがあります。
解答に必要な情報を読み落としていないか、問題をもう一度よく読んでみましょう。
【目安の解答時間】
1分30秒~2分30秒での解答を心がけましょう。
計算が必要になるものの、設問文も短く問題の構造はシンプルですし、手がかりとなる資料も少ないため、扱う情報は小量ですから、必要となる時間はそれほど多くありません。いかに速く正確に計算できるかが鍵を握ります。
産業・貿易に関する問題の攻略の方法
主に問2または問3で出題される産業・貿易に関する問題についてみていきます。
【出題の傾向】
<過去の出題内容>
- 平成11年度
問2:農畜産物についての記述のうち、オーストラリアについて述べたものを選ぶ
問3:工業の発展について述べた文章と日本との貿易品目別割合のグラフを手がかりに、略地図中のうち、中国に当てはまるものを選ぶ - 平成12年度
問3:工業の発展や日本との貿易について述べた文章と綿糸の国別生産量の割合を示したグラフを手がかりに、略地図中のうち、アメリカに当てはまるものを選ぶ - 平成13年度
問1:GDP、貿易額を示した表を手がかりに、略地図中のうち、東南アジアに当てはまるものを選ぶ
問2:農業・工業についての記述のうち、ユーロポートについて述べたものを選ぶ
問3:日本への輸出総額、輸出品と割合を示したグラフのうち、ブラジルに当てはまるものを選ぶ - 平成14年度
問1:穀物生産量・穀物国内消費量を示した表のうち、アメリカに当てはまるものを選ぶ。
問2:ある国の農業について示した表と農業・工業について述べた文章を手がかりに、略地図中のうち、フランスに当てはまるものを選ぶ
問3:気候や農業についての記述のうち、アフリカについて述べたものを選ぶ - 平成15年度
問2:産業別の就業人口の割合を示したグラフと産業の特色を述べた文章を手がかりに、略地図のうちから、イギリスに当てはまるものを選ぶ
問3:輸出相手国と輸出品目を示した表を手がかりに、略地図中のうち、オーストラリアに当てはまるものを選ぶ - 平成16年度
問1:面積や農作物について示した表を手がかりに、略地図中のうち、アルゼンチンに当てはまるものを選ぶ
問3:輸出相手国と輸出品目を示した表を手がかりに、略地図中のうち、スウェーデンに当てはまるものを選ぶ - 平成17年度
問1:鉄鉱石の日本への輸出額と生産高を示した略地図と面積・平均気温や貿易相手国を示した表を手がかりに、チリとフィリピンを選ぶ
問3:原油や経済成長について述べた文章を手がかりに、原油の産出量・消費量、国内総生産について示した表のうち、中国に当てはまるものを選ぶ。 - 平成18年度
問2:略地図を手がかりに、小麦、米、大麦、大豆の生産量について示した表のうち、小麦に当てはまるものを選ぶ
問3:産業について述べた文章を手がかりに、小麦の輸出量・輸入量と農業経済活動人口の割合を示した表のうち、インドに当てはまるものを選ぶ - 平成19年度
問1:略地図を手がかりに、輸出額、輸入額、日本との貿易額の割合を示した表のうち、東南アジアに当てはまるものを選ぶ
問2:実質経済成長率の期間ごとの平均と輸出額・輸出品について示した表を手がかりに、貿易の様子について述べた文章のうちから、カナダについて述べたものを選ぶ
問3:略地図と文章を手がかりに、輸出相手国の変化を示した表のうちから、ポーランドに当てはまるものを選ぶ - 平成20年度
問3:貿易黒字と産業について述べた文章、日本への輸出額・輸出品と日本からの輸入額・輸入品を示した表を手がかりに、略地図中から中国を選ぶ - 平成21年度
問3:日本への食料輸出や貿易相手国について述べた文章と2つの表を手がかりに、略地図中からニュージーランドに当てはまるものを選ぶ - 平成22年度
問2:原油の産出量や貿易相手国、輸出品目を示した表のうち、メキシコに当てはまるものを選ぶ
問3:総生産額と人口の変化を示した略地図を手がかりに、地図で示された地域について述べた記述を選ぶ - 平成23年度
問3:輸出額や貿易相手国について述べた文章と2つの表を手がかりに、略地図中からマレーシアに当てはまるものを選ぶ - 平成24年度
問2:自動車生産台数や輸出品目、日本との輸出額・輸入額の割合を示した表のうち、大韓民国に当てはまるものを選ぶ
問3:平均経済成長率と日系自動車会社の工場数を示した略地図とそれについて述べた文章を手がかりに、タイを選ぶ - 平成25年度
問2:日本への輸出品目や鉄鉱石の生産量などを示した表を手がかりに,略地図中から南アフリカに当てはまるものを選ぶ
問3:日本との貿易総額と日本への輸出品目と示した略地図とそれについて述べた文章を手がかりに、スイスを選ぶ - 平成26年度
問2:産業の発展や貿易収支について述べた文章を手がかりに、輸出額・輸入額や国内総生産を示した表のうち,イギリスに当てはまるものを選ぶ
問3:貿易総額や日本への輸出に述べた文章を手がかりに,輸出額と日本の輸入額・輸入品目を示した表と略地図のうち,マレーシアに当てはまるものを選ぶ
※産業・貿易に関する情報だけでなく、時差や自然環境、歴史についての記述を合わせて手がかりとする場合もあります。
<出題パターンの分析>
毎年必ず出題されており、都立入試の社会に特有なタイプの問題です。地図はもちろん、表やグラフ、文章など、複数の資料を同時に読みながら情報を処理することによって正解を導きます。
記号で解答する形です。
<求められている能力>
学校の定期テストではめったに見られないタイプの問題です。ふだん社会が得意でも、この出題形式に慣れていないと戸惑うことは間違いありません。
・略地図中に示された位置から国や都市、地域の名称を導き出す力
・各国の産業や貿易の特色についての知識
・複数の資料から情報を読み取り、処理する力
・表やグラフから特徴的な項目や数値の変化を読み取る力
・割合を計算する能力
が求められています。
<今後の出題予測>
大問2においての必出パターンなので、今後も毎年出題されると考えて間違いありません。3問中2問,すなわち、15点中10点に直結するので、対策は必須といえます。
【攻略の手引き】
大問3の中でも最も複雑な出題形式です。知識があってもうまく活用できないと得点できません。
過去問を素材にこのタイプの問題を数多く解いて慣れておく必要があります。
また、試験当日も、冷静かつ慎重に問題をよく読み考える必要があります。
それでは、具体的な攻略法です。
-
ポイント1:設問文のラスト1文を読み、“問われていること”を正確に把握する
設問文が5、6行と非常に長いのが特徴です。読んでも「何が聞かれているの?」と混乱してしまうような構造になっています。そこで、まず最後の1文を読むことから始めましょう。例外なく、“問われていること”は最後の1文に書かれています。解答する上での条件(記号はア〜エなのか①〜④なのかAからDなのか、など)も同様です。
見落としのないように丁寧に読み、アンダーラインを引いたりマルで囲んだりして、目立たせましょう。その上で、設問文を頭からもう1度読んでみましょう。 -
ポイント2:略地図に国名を書き込む
地図上で示された国や都市の名前がわかることが前提です。また、位置情報自体が大きなヒントになることもあります。
ですから、国名を地図の中に書き込むという“下準備”は必須です。なお、地図上で示された複数の国の候補は問題文の中に書かれています。これも踏まえて、素早く済ませてしまいましょう。
-
ポイント3:ヒントとなる文章は念入りに読み取る
「〜の文章で述べている国に当てはまるのは、〜のうちのどれか」という出題の場合は、真っ先に示された文章を読み進めます。そうでない場合でも、文章があればこれは大きな手がかりです。
この中からいかにヒントをつかむかがすべて、と言っても過言ではありません。例1)平成26年度の問2
文章:「貿易赤字が続いている」
ヒント:輸出額より輸入額が多い例2)平成26年度の問3
文章:「貿易総額は3600億ドルで、そのうち輸出額5割を超えている」
ヒント:輸出額は1800億ドル以上例3)平成26年度の問3
文章:「1990年と2010年を比べると、この国からの日本の輸入額は約2.5倍に増えており、現在は液化天然ガスの閉める割合が高い」
ヒント:2010の輸入額÷1990年の輸入額≧2.5
ヒント:日本の現在の輸入品に液化天然ガスが含まれているというように、文章中からヒントになりそうなところを拾い出していきます。いかに“ピンとくる”かが鍵を握りますから、読むのが苦手なら2回3回と読む必要があります。
-
ポイント4:産業や貿易についての表を1つずつ検討していく
ポイント3まででつかんだヒントから、表中の情報を見比べて、該当する国を探っていきます。輸入・輸出の総額や輸出品の構成や変化が表から読み取れます。「輸出額<輸入額となっているかどうか?」
「輸出額は1800億ドルを超えているかどうか?」
「2010の輸入額÷1990年の輸入額≧2.5となるかどうか?」
「日本の現在の輸入品に液化天然ガスが含まれているかどうか?」
と問いかけながら、○×をつけていきます。このときに、各国の主な産業や輸出品の知識があると、一気に正解に近付けます。特に、日本が輸入している品目からどの国なのかが判断できると有利です。
なお、貿易総額の多い相手国が3つ示されている場合もあります。地理的に場所の近い国が貿易相手の上位にくることが多いので、これもヒントになります。ただし、アメリカ合衆国は例外です。この国とは世界中の多くの国が貿易をしているため、アメリカ合衆国に近いとは限りません。
以上のように順に検討しながら、該当しない国は選択肢に×をつけて消去していきます。
-
ポイント5:問われていることに対応するように選択する
表や略地図中から選ぶ場合もあれば、別の箇所から選ぶ場合もあります。多くの中学生が模試で「わかっていたのにうっかり違う記号を書いてしまった」というミスをした経験があるはずです。ポイント4できちんと消去法を用いておくと、そうしたミスは防げます。また、解答欄に記入する前に、ポイント1でチェックしておいた、解答の条件に合った解答ができているかも最後に確認することも必要です。
【目安の解答時間】
2分〜3分での解答を心がけましょう。
知識の量よりも知識の活用法がものをいいます。与えられた資料から解答に必要な情報を汲み取り、頭を回転させて情報を処理します。問題を読んですぐに解答できる、ということはまずありません。
時間をかけてでも、丁寧に取り組む必要があります。知識に自信がなくても資料から正解にたどりつくこともできます。消去法を使うことで、正解確率は上がるのですから、根気よく挑みましょう。
中学1・2年生はどんな勉強をすればいいか?
これから受験に向けての準備を進めて行く中学1・2年生も、今のうちから行える対策があります。
定期テストの点数だけを意識するのではなく、先々を見据えて普段の学校の授業や家庭学習に取り組んでおくのが絶対におすすめです。
特に、次のような点を意識しながら、勉強して欲しいと思います。
【気候・自然環境に関する問題】
- 世界地図の知識は必須。地図上で国名と位置がすぐに言えるようにしておく。近年は、問題文中で国名ではなく都市名が挙げられることが多いので、首都や主要な都市から国名がいえるようにしておくと更に良い。
- 世界地図については、普段よく目にするメルカトル図法だけでなく、正距方位図法やモルワイデ図法の見方も身につけておくとよい。
- 雨温図も必出と考え、読み方を早くからマスターしておく。雨温図を見ただけでどの地域の気候帯がわかるようにしておくのが望ましい。世界地図上で気候帯を色分けし、そこに該当する地域の雨温図を貼り付けたノートを作っておくのがおすすめ。
【時差に関する問題】
- 「経度差15度で時差1時間」という公式をしっかりと頭に入れた上で、教科書や問題集で実際に時差を求める練習を数多く行う。
- 時差の基本事項以外の知識は特に求められていないので、中1のうちから思い切って過去問で時差の問題に触れてみる。慣れるし自信もつく。
【産業・貿易に関する問題】
- やはり世界地図の知識は必須。地図上で国名と位置がすぐに言えるようにしておく。
- 各国の主な産業(農林水産業、鉱工業)については確実に覚えておきたい。学校の授業で習った範囲については、ノートや教科書、資料集を元にまとめておくとよい。
- 主要な輸出品についても同様。主要な輸出品は産業と密接に関わるので、産業とセットで考えると覚えやすい。特に、日本との貿易関係が問われるので、日本への輸出品は確実に覚えておきたい。
- 世界の地理については1年で学習するため、2年生でも早いうちから対策が可能。特に都立入試特有の出題形式なので、慣れていないと非常に難しい。早いうちに過去問に触れておくのも有効。
是非、参考にしてみてください。
この章に関係のある記事はこちら
執筆
石井 知哉(いしい ともや)