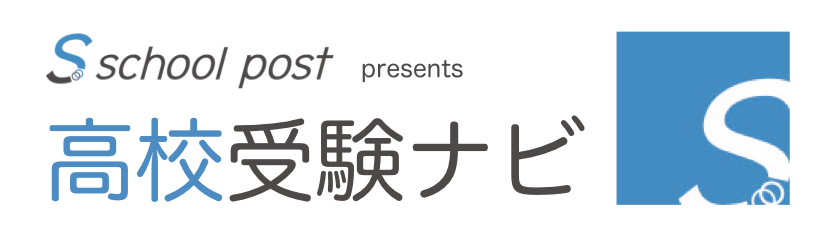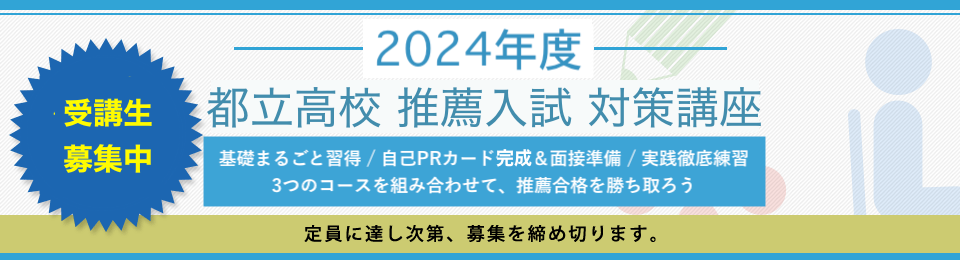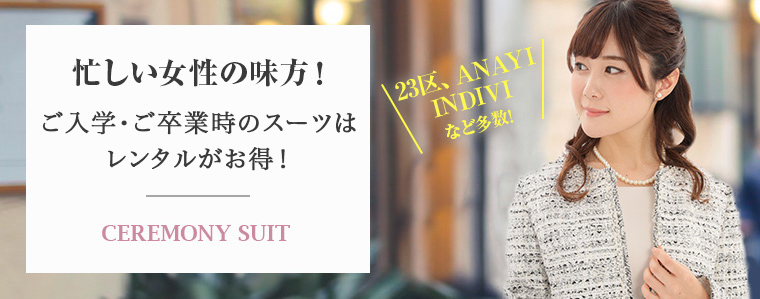「授業態度」の評価を上げるために最初に見直すべきこと

執筆
石井 知哉(いしい ともや)
内申点は観点別で評価されている
まず知っておきたいのは内申点の評価の仕組み。地域や学校によって細かい違いはありますが、基本的には「関心・意欲・態度」「技能」「知識・理解」「思考・判断・表現」で分けられた観点別に評価がされます。それらの全体評価が評定として1~5(または1~10)によって数値化されているのです。
さらに、それらの判断基準は大きく分けて「定期考査(テスト)」「授業態度」「提出物」の3つだと言われています。もちろん上記以外の学校生活も評価対象から外れているわけではありませんので、ご注意ください。
観点別評価について詳しく知りたい方は以下よりお進みください。
この章に関係のある記事はこちら
授業態度に関するやってはいけない内申点を下げる行為
授業態度は、主に授業中に授業を受ける姿勢・気持ちを評価します。観点でいうと「関心・意欲・態度」の評価に大きく影響するのも授業態度でしょう。「授業を受けている・聞いている」だけでは少し足りません。「授業内容に“関心が強く”“意欲的に”受けている・聞いている」と思われて、ようやくいい評価がもらえるのです。反対に「関心も低く、意欲もない」と評価されれば、低評価は免れません。
具体的には、以下の行動が「関心が低く、意欲がない」と判断されます。
- 授業開始時に席に着いていない
- 授業の道具(筆記用具、教科書、ノート、プリント)が机に出ていない
- ボーッとしている /授業とは関係ないことを考えている / よそ見
- 居眠り / あくび
- 猫背 / 膝を立てる / 頬杖(ほおづえ)をつく
- 立ち歩く /消しゴムをちぎって投げる
- 携帯電話をいじる
- チョコやアメなど、お菓子を食べる
- 友達との授業に関係ないおしゃべり /友達と手紙交換
- 先生を呼び捨て、「センコー」呼ばわり、あだ名呼び
- 注意に対する無意味かつ無根拠の言い訳、反論
上記の他にも、たくさんあるのは言うまでもありません。授業中の態度は普段の家庭での生活が影響する場合が多くあります。授業中にボーッとしている、居眠りをしてしまうなどは睡眠時間が少ないことが原因のケースもありますし、姿勢や態度そのものは、家庭での生活がそのまま反映することもありますから。
以上が授業態度に関する「内申点を下げる、やってはいけない行動」です。 今回ご紹介したのが全てではありません。紹介された中で、「うちの子が当てはまるのはなかったわ」と思われた親御さんも、安心するのはまだ早いのです。「下げる行動をしていない」=「内申点があがる」ではありませんから。
その他「提出物(宿題)」「定期考査(テスト)」についての振り返りは以下よりお進みください。
この章に関係のある記事はこちら
執筆
石井 知哉(いしい ともや)