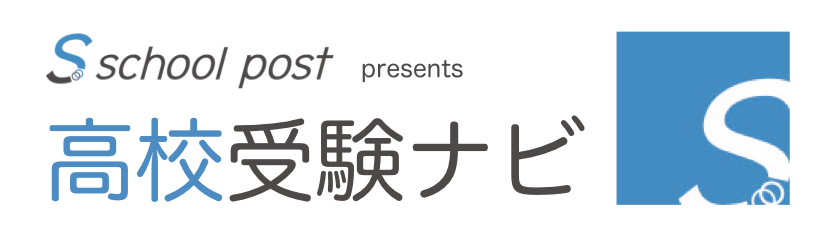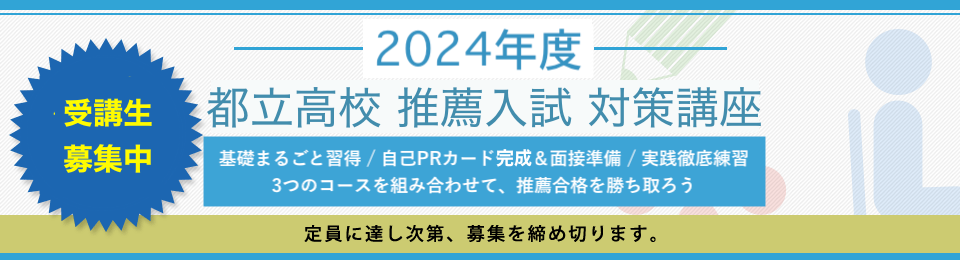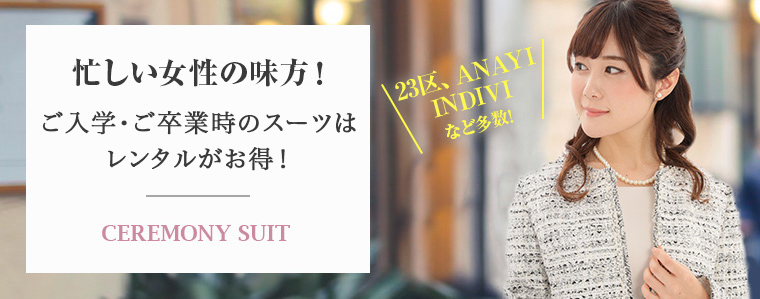中学技能教科「技術」攻略、「生物育成」技能についての基礎知識

その実習で行った知識から定期テストに出題されるケースが多くあります。
そこで今回は、植物を育てるために必要な技能についての基礎知識を解説します。
執筆
中里 太一(なかざと たいち)
土づくり
培養土の場合、小粒の赤玉土と腐葉土を2対1で混ぜます。その理由は主に2つあります。
- 赤玉土は通気・排水性が高いから
- 腐葉土は保水・保肥性が高いから
この2つが混ざることによって、適度な水分と空気をとどめることができます。
種まき
種のまき方と様々な種類をおさえておきましょう。
(1)種まきのやり方
- 培養土をポットに詰める
- ポットに種を3,4粒均等に入れて、3~5ミリ指先で押し込む
- 5ミリくらい土をかけ、表面の土を手で優しく押さえる
(2)種まきの種類
- じかまき…直接花壇や畑にまく方法
- 箱まき…育苗箱などに種をまく方法
- ポットまき…ポリポッドなどに種をまく方法
- 点まき…5~10センチの穴をつくり、その穴に種をまく方法
- すじまき…土に溝を作り、その溝に一列に種をまく方法
- ばらまき…土をかぶせず種が重ならないように種をまく方法
植物ごとに向いているまき方があります。テストには実習で行ったまき方が出題される可能性が高いので覚えておきましょう。
生育
種をまいてから、植物が生育する過程についても、覚えておくべきことがたくさんあります。整理しながら確認しておきましょう。
■ 間引き
間引きとは、種を多くまいた後で、苗の品質や発育をそろえるために、栽培に適した苗を残すことです。
■ 移植・定植
(1)移植:植物を植える場所を変えること
(2)定植:仮植えしたものを最終的に植え替えること
-
定植の注意点
- 抜いた苗はまっすぐに置く
- 株の根本に土を加え、手で押さえて、根と土の間に空間ができないようにする
- 支柱は根を傷つけない位置に立てる
■ かん水
かん水とは、植物に水をあげることです。
-
かん水の注意点
- 土の表面が乾いてからかん水をする
- かん水は排水口から水が出るまで行う
- 受け皿を使用している場合、たまった水は捨てる
かん水でもっとも大切なことは「古い水と空気を、新鮮な水と空気に入れ替えること」です。
その基本を忘れなければ、たとえば「受け皿にたまった水はそのままにしてもよい。〇か×か」という正誤問題が出題されても対処できます。
水を受け皿にためてしまうと、その水は古くなるわけなので、植物にとっては良くないことです。受け皿にたまった水は捨てるという知識を覚えていなくても、この問いは×だと判定できます。
■ 誘因
誘因とは、植物の茎が、倒れないように茎と支柱をひもで結ぶことです。
きつく結ぶと、養分が上に行かなくなってしまうため、茎はゆるく結ぶよう注意が必要です。
■ 養分の管理
植物の生育に必要なものは、二酸化炭素・酸素・水・養分です。
-
養分の与え方
- 元肥:定植の前に初期の成長を促すために与える
- 追肥:生育状態に応じて肥料が不足しないように与える
■ 摘芽・摘しん
- 摘芽:わき芽を取ること→茎の先端部の成長を促す
- 摘しん:茎の先端部を切ること→結実やわき芽の成長を促す
受粉・収穫
(1)受粉
-
受粉のポイント
- めしべにおしべの花粉をつけること
- 風などで花房が動かない場合は、人の手で花房を振って受粉させる
(2)収穫
-
収穫のポイント
- 農作物をとりいれること
- 収穫の時期は大きさ・色・形・開花からの日数で判断する
以上が、生物育成分野の基礎技能に必要な知識です。
土のつくり方~収穫まで植物の生育段階ごとに必要な用語を解説しました。
基本的なことはほぼ網羅されています。
注意点としては、冒頭でも説明したように、この分野は授業内で扱った植物についてのことを具体的にきいてくる問題が非常に多くの学校で出題されています。
たとえば授業内で育てたトマトの品種を答えなさいという出題がされる学校もあります。授業で配布されたプリントや授業で扱った題材はかならず覚えておくことをお勧めします。
執筆
中里 太一(なかざと たいち)