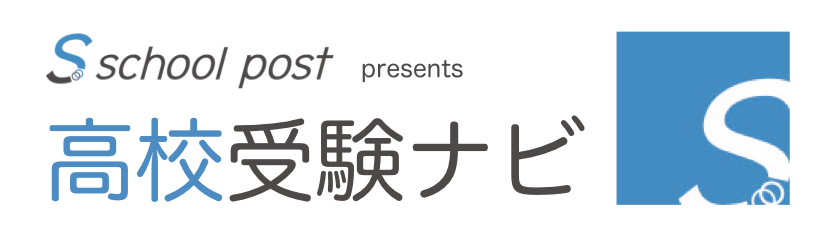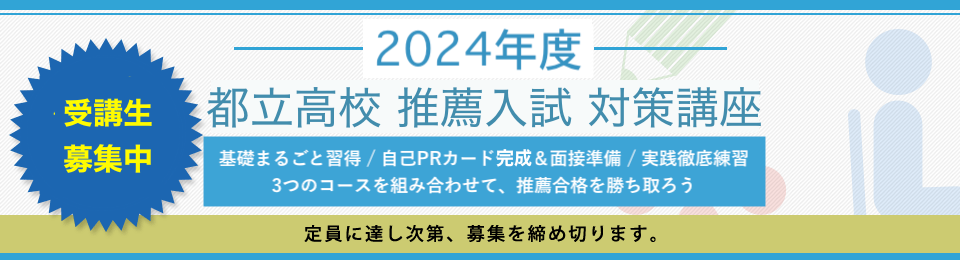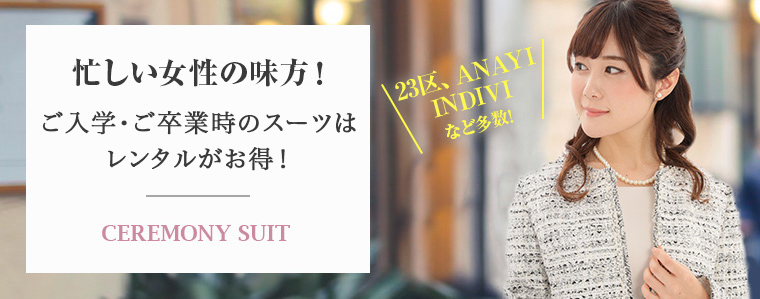中学技能教科「技術・家庭科」攻略、食品分野で定期テストに出題されること

家庭科の食品分野で出題される「生鮮食品と加工食品の違い」と「食品の選択」の2項目について実際の定期テストで出題されるポイントと出題例を紹介していきます。ここで紹介したことを押さえておくことが定期テストの高得点につながります。
執筆
中里 太一(なかざと たいち)
生鮮食品と加工食品
まずは生鮮食品と加工食品について勉強のポイントと、定期テストで出題されることを紹介します。
(1)用語を覚える
- 生鮮食品
野菜、魚、肉、卵など生産地でとれたままの食品のこと - 加工食品
生鮮食品にさまざまな加工をした食品のこと
(2)それぞれの食品の特徴を覚える
生鮮食品は特徴を覚える
- 短期間で食べきらなければいけない
- 旬、出盛り期がある
※旬=野菜や果物では露地で栽培したときに多く取れる時期。魚では、脂ののった時期のこと
※出盛り期=市場への入荷量が一番多い時期のこと
旬や出盛り期は言葉だけではなく具体例まで覚える
- 春:さわら、にしん、たけのこ、アスパラガス
- 夏:あゆ、かつお、トマト、なす
- 秋:さんま、さけ、さつまいも、れんこん、しいたけ
- 冬:ぶり、たら、ホウレンソウ、はくさい
加工食品は保存性を高める加工の仕方と具体例についても覚える
| 加工の仕方 | 具体例 |
| 乾燥させる | 煮干し 干しブドウ 干ししいたけ |
| 塩漬け、砂糖漬けにする | 梅干し 甘納豆 ジャム |
| 加熱し、密封する | 缶詰 瓶詰 レトルト食品 |
| 温度を下げる | 冷凍食品 |
(3)出題例
- 店で選ぶ食品は大きく分けると加工食品と何食品か? 漢字2字で答えなさい。
答え:生鮮 - 野菜や肉などを加工する前の食品を何というか。
答え:生鮮食品 - みかん・ほうれんそう・たらの旬はどの季節か?
答え:冬 - 食品の保存性を高める工夫にはどのようなものがあるか? 簡単な説明と例を挙げなさい。
解答例:(説明)乾燥させる (例)煮干し、干しブドウ、干ししいたけ
食品の選択
ここからは食品の選択についての勉強のポイントと定期テストで出題されることを紹介します。
(1)生鮮食品の選び方は常識で判断。ただし肉、魚の鮮度の見分け方については覚える必要がある
肉の鮮度の見分け方
- 嫌な臭いがしない
- ドリップ(液汁)がでていない
- 弾力がある
- ぬるぬるしていない
魚の鮮度の見分け方
- 目が澄んでいて透明感がある
- エラがきれいな赤色
- 身が締まって弾力がる
- 腹部が裂けていない
- うろこが剥げていない
(2)食品の表示やマークを見て何を意味するのかを答えられるようにする
記載されなければいけないこと
- 生鮮食品
名称、原産地 - 加工食品
名称、原材料名、内容量、期限、保存方法、製造者の名称と住所
加工食品の原材料名は、食品添加物、食物アレルギーの原因となる食品・遺伝子組み換え食品を含む場合も表示される
※食品添加物=品質の改良や保存性の向上、着色や調味などを目的として加えられるもの
期限の注意点
期限は、消費期限と賞味期限に分かれます。それぞれの違いが出題されます。
- 消費期限
衛生的に安全に食べられる期限。弁当や食肉など品質が劣化しやすいものに表示される - 賞味期限
スナック菓子や即席めんなど比較的長く保存が可能なものに表示される
(3)出題例
- 鮮度の良い食品(たとえば、あじ)を購入したいとき、適さないものはどれか?
a:身が締まっている
b:エラが赤い
c:目が澄んでいて透明感がある
d:うろこが剥げている
答え:d - 生鮮食品につけることが義務付けられている内容を2つ答えなさい。
答え:名称、原産地 - 2018年12月が賞味期限のものを2019年1月1日に食べるのは体調を崩す可能性がある。○か×か?
答え:×
以上が「生鮮食品と加工食品の違い」と「食品の選択」の学習のポイントと定期テストの出題例です。特に「生鮮食品と加工食品の違いと特徴」は出題頻度が高いです。用語・意味に加えて具体例を覚えることが大切です。高得点を取れるようがんばってください。
執筆
中里 太一(なかざと たいち)